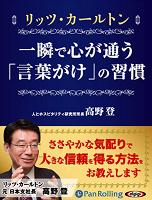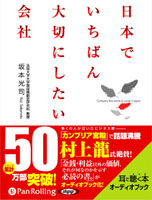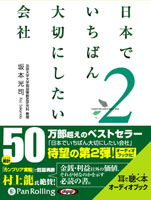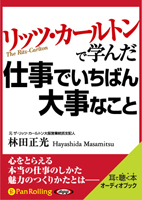|
著者、坂本光司先生より
本書出版に纏わる熱い想いをコメントいただきました。
↓↓再生はこちら↓↓
play
【担当編集者のコメント】
『日本でいちばん大切にしたい会社』以来、ずっと坂本光司先生の担当をさせていただいていました。何度も先生とお目にかかるなかで、先生が「大学の講義や講演会でこういう話をすると、大きくうなずいている方がたくさんいるんですよ」とおっしゃってくださったことがあります。
「こういう話」というのは、先生が6,500社にも及ぶ企業訪問と研究のなかで、気のついたことをまとめたメモ書きのようなものでした。そのメモ書きを拝見して、自分自身も経営に当たっているものとして、強く首肯せざるをえない箴言が数多くあることに気づきました。そこで先生に強くお願いし、本書の出版の運びとなりました。
経営者だけでなく、会社で働く多くの方々にも示唆深い内容がふんだんに詰め込まれた100の言葉。きっと、大切なことに改めて気づき、確認するきっかけをつくってくれると思います。
【著者のコメント】
私はおよそ20年くらい前から、経営者など多くのリーダーとお会いし、さまざまな人々の言動を見るなかで、感じたこと、気がついてほしいことを言葉にしてきました。そうした「語録」を一覧表にしたメモを、私は「坂本教授のなるほど経営語録50選」と名づけました。当初のメモの数は50だったのです。その後増えても、70程度でした。 その語録の一部を、私は毎週開催される社会人学生を対象とした大学院での講義や、経営者や経営幹部向けの研修会で紹介してきました。
やがてこの拙い語録は、徐々に全国各地の人の目にふれていき、たくさんの方から「1冊の本にまとめてほしい」という要望をいただくようになりました。 しかし今回もまた、出版までは苦しい日々が続きました。すでにつくった語録は70程度ありましたが、これを機会に100の語録を紹介しようと考えたからです。また、その語録の意図するところを、限られた文字数で解説する必要があったからです。
この本が、日々一生懸命に生きている方々のよりどころとして、少しでもお役に立てればと思います。
目次
はじめに
1 経営者PART1
1◆経営とは、会社(組織)にかかわるすべての人々の永遠の幸せを
実現するための活動のことである。
2◆経営においては、常に“五人”の幸福を念じ、その実現を図らねばならない。
3◆経営者がいやなこと・望んでいないことを、社員が望んでいるわけがない。
4◆「教える教育」ではなく、「教えさせる教育」こそ最高の教育である。
5◆人財はアメやムチではなく、正しい経営のなかから自然に育つ。
6◆社員がやる気を喪失する最大の要因は、経営者や上司に対する「不平、不満、不信感」である。
7◆経営者・管理者の最大の使命は、部下を管理(マネージ)することではなく、
フェロー(メンバー、仲間)をリード・支援することである。
8◆社員が求める経営者像・管理者像は明確である。
9◆企業は企業それ自身のためにあるのではなく、企業構成員のために存在する。
10◆人財が最も嫌うのは、「管理」という名の刃物である。
11◆正しいことをしようとしている人の邪魔になるルールには、
片目をつぶってしまうことだ。
12◆経営者に楯突く社員には二つのタイプがある。見誤ると人財を失う。
13◆人財が強く求めているのは金、ステータスなどではなく、愛・命である。
14◆「一生懸命」という名のもとに行われる間違った言動を認め、放置してはならない。
2 経営者PART2
15◆経営者の最大・最高の使命である決断は、
いつの時代も「正しいか、正しくないか」「自然か、不自然か」を軸に行う。
16◆超優良企業の経営者は、景気や流行は決して追わない。
17◆前へ前へと進まない経営者・リーダーは、年齢を問わず老害である。倫理観・正義感が
著しく欠落した人には、経営者の資格がない。ともに組織を去るべきである。
18◆経営者の最大の仕事は三つだけである。
19◆経営者とは、「経営」という仕事を中心にやる社員のことである。
20◆同一組織において、組織の長を超える人財は決して育たない。
21◆世のため、人のためにならない制度や慣習は、
今日のリーダーたちが創造的破壊をしなければならない。
22◆経費には、ケチってもよいものと決してケチってはいけないものがある。
23◆経営者・管理者が重視すべきは「業績」ではなく「継続」である。
24◆社員を路頭に迷わせるなら、経営者も一緒に路頭に迷うべきである。
25◆企業経営の成否は、すべてトップにかかっている。
使命と責任が果たせない経営者は、潔く退出すべきである。
26◆悪は徒党を組むが、誠実な人は決して徒党を組まない。
27◆社員に定年があるなら、経営者にも定年があるのが当然である。
28◆経営者の定年のシグナルは三つある。
29◆社長と会長の最大の違いは、「我慢の度合い」である。
30◆経営者やリーダーは、常に自らに強い圧をかけて生きよ。
3 人財
31◆業績が高い会社のモチベーションが高いのではなく、
モチベーションが高い会社の業績が高いのだ。
32◆経営の三要素は、一に人財、二に人財、三に人財であり、
ほかのものはそのための道具にすぎない。
33◆帰属意識・仲間意識の醸成は、喜びも悲しみも苦しみも、ともに分かち合うことから始まる。
34◆「CS」を飛躍的に高めたいなら、その前に、「ES」を飛躍的に高めるべきである。
35◆企業の最大の商品は、・社員・という名の商品である。
36◆社員と顧客が強く求めているのは経済的豊かさ・物質的豊かさではなく、
心の豊かさ・脳の豊かさである。
37◆人財問題は、「確保」「育成」「評価」の三つに大別できる。最も重要なのは「評価」である。
38◆超優良企業の賃金制度は過度な「成果主義型」ではなく、「年功序列型」「年齢序列型」である。
39◆人財は好不況にかかわらず、求め続けるべきである。
40◆大事なのは入社倍率ではなく、離職率である。
4 顧客
41◆顧客が求めているのは、免責サービスではなく感動サービスである。
42◆お客様とのよい関係を長く続けたいなら、どんなときでも、どんな場面でも、
お客様にとっていちばんよいと思うことをし続けなければならない。
43◆最高の営業は、「営業をしないこと」である。
44◆商圏を決めるのは、企業ではなく顧客である。
45◆“売れる商品”ではなく、“買ってくれる商品”を創る。
46◆顧客には「現在顧客」と「未来顧客」がいる。
47◆モノの値段は、企業の原価計算で決まるのではなく、市場・顧客が決める。
48◆売れない商品には、一一の共通する特徴がある。
49◆企業にとっては一%の不良品でも、
それがたまたま当たった顧客にとっては一〇〇%の不良品である。
50◆企業の真実は、電話一本でよくわかる。
5 企業と経営PART1
51◆企業は私的なものではなく、社会的公器である。
52◆明確な経営理念がない企業の社員や、それが心に深く浸透していない社員は、
方向舵のない飛行機や船に乗っているようなものである。
53◆世のなかに弱者は二種類ある。
私たちが尽力しなければならないのは、いつの時代も「真の弱者」に対してである。
54◆正しい経営、偽りのない経営は滅びない。
55◆次代(時代)は五つの眼で読む。
56◆経営学は「終わりから始める学問」である。
57◆異常を基準にすると、正常があたかも異常に見える。
異常が長く続くと、異常があたかも正常に見える。
58◆企業の盛衰は需要の原理ではなく、供給の原理、
つまり「有効供給の有無」によって決まる。
59◆いつの時代も「マクロ」ではなく、「ミクロ」が次代を創る。
60◆超優良企業は、単にビジネスモデルが優れているだけではなく、
企業自身の「社会価値」が優れている。
61◆企業に日常的に付加価値をもたらしてくれるのは、顧客である。
したがって、企業の組織図は「ピラミッド型」ではなく、「逆ピラミッド型」にすべきである。
62◆中小企業には、決してやってはいけない三つの競争がある。
63◆経営者が重視すべきは、五つの財務指標である。
64◆損益計算書は、“五人”が経営者に与えた唯一の通信簿である。
65◆マネジメントの問題の大半は、外ではなく内にある。
66◆問題とは「あるべき姿マイナス現状」のことである。
問題を可能な限り数値化・見える化することだ。
67◆マネジメントに関する問題の大半は、目的そのものに関する問題である。
68◆変化及び変化から発生する問題には、二つの種類がある。
69◆七〇%の企業が赤字状態になっているが、それでも問題は外にはない。
70◆問題には現象問題と本質問題の二つがある。経営者が対処すべきは、本質問題である。
6 企業と経営PART2
71◆経営活動のなかで不可能なことは少ない。ただただ、時間がかかるだけである。
73◆経営とは差別化のことである。差別化しない限り、経営の使命と責任は果たせない。
74◆「下請け」は、永遠に続ける経営形態ではない。
75◆万年赤字会社につける唯一の薬は、万年赤字を認めないことである。
76◆不況は経営者ばかりか、社員の本性も顕在させる。
だからときどき不況になったほうがよい。
77◆不確実な未来を憂慮するより、確実な未来に備えよ。
78◆冷たい大企業が中小企業に選別され、捨てられる日は近い。
79◆誰かの犠牲の上に成り立っているビジネスモデルが、正しいはずがない。
80◆近年の企業間格差は、第四の経営資源力格差である。
81◆中小企業と大企業は本来、対比させるべき存在ではない。生きる世界が違うのである。
82◆業種分類不可能型企業経営は、不安定・不確実な時代を生き抜く一つの道である。
83◆時代(次代)は二・五次産業を求めている。
84◆本社は限りなく小さいほうがよい。本社社員は本社の正当性を示すため、
次から次に「管理」というくだらない仕事をつくるからだ。
85◆行政のやりすぎは、経営者や社員のやる気をそぐ。
86◆労使はパイを奪い合う関係ではなく、新しい価値をともに創造する関係であるべきだ。
87◆わが国の未来を決するのは、工業ではなく農業である。
88◆国や県など、行政機関がなんと言おうと、
審議会や委員会の人選を見れば本気かポーズかがよくわかる。
7 働く・生きる
89◆人はお金のためではなく、愛する人のため、幸福になりたいために働いている。
90◆真の価値とは、世のため、人のためにかく汗のことである。
91◆人の幸福は、働くことをおいて得ることは不可能である。
92◆訂正のきかない過去に思いを馳せるより、明日を夢見て今日を精いっぱい生きるべきだ。
93◆私たちがやらない、やれないよいことをしている人を見つけたら、
私たちがやることはその人を支援してあげることである。
94◆正しい企業に対し、私たちができることの一つは、その企業の顧客になることである。
95◆一%の素敵な人に出会いたいならば、一〇〇%の人々と積極的に会うべきである。
96◆真の平等とは、不平等に対しては、不平等の扱いをすることである。
97◆障害者や高齢者の雇用に尽力しない人々は、
「自分や家族は障害者や高齢者に絶対にならない」と言っているのと同じである。
98◆多くの日本人は「豊かさの貧困」状態にある。
99◆真の強者は弱者にやさしい。
100◆人のやさしさは、涙の量に比例する。
エピローグ
企業の目的は永遠の幸福の追求と実現
【心理・その他】
坂本 光司(さかもと・こうじ)
福井県立大学教授・静岡文化芸術大学教授等を経て2008年4月より法政大学大学院政策創造研究科(地域づくり大学院)教授及び法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科(MBA)客員教授。他に、国、県、市町や商工会議所等団体の審議会や委員会の委員を多数兼務。専門は中小企業経営論・地域経済論・産業論。
近著
『日本でいちばん大切にしたい会社3』 著 あさ出版 2011年
『日本でいちばん大切にしたい会社2』 著 あさ出版 2010年
『日本でいちばん大切にしたい会社 』 著 あさ出版 2008年
『経営者の手帳 働く・生きるモノサシを変える100の言葉』 著 あさ出版 2010年
『中国義烏ビジネス事情』 編著 同友館 2008年
『私の心に響いたサービス』 著 同友館 2007年
『消費の県民性を探る』 編著 同友館 2007年
『選ばれる大企業・捨てられる大企業』著 同友館 2007年
『地域産業発達史』 編著 同友館 2005年
『この会社はなぜ快進撃が続くのか』 著 かんき出版 2004年
他多数
※本商品は『経営者の手帳 』[あさ出版刊 /坂本光司著 ISBN:978-4-86063-430-8 1,470円(税込)]をオーディオ化したものです。 (C)Koji Sakamoto
|
関連商品
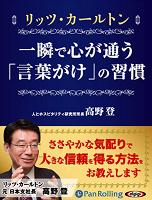
[オーディオブック]
リッツ・カールトン 一瞬で心が通う「言葉がけ」の習慣
[著]高野登
1,500円 (税込)

[オーディオブック]
最強の「ビジネス理論」
集中講義
[著]安部徹也
/日本実業出版社
1,600円 (税込)
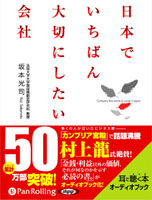
[オーディオブック]
日本でいちばん
大切にしたい会社
[著]坂本光司
1,400円 (税込)
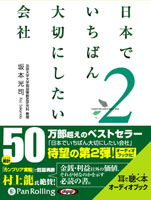
[オーディオブック]
日本でいちばん
大切にしたい会社2
[著]坂本光司
1,400円 (税込)

[オーディオブック]
あらゆることが好転していくご挨拶の法則
[著]林田正光
1,500円 (税込)
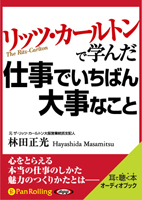
[オーディオブック]
リッツ・カールトンで学んだ 仕事でいちばん大事なこと
[著]林田正光
1,800円 (税込)
|
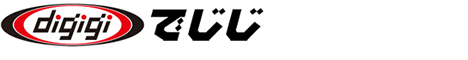
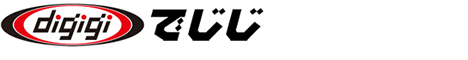

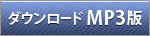
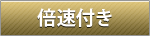 約183分 222ファイル 倍速付き 2011年11月発売
約183分 222ファイル 倍速付き 2011年11月発売